自分が何を望んでいるのか、何のためにがんばっているのか、よくわからなくなってしまうくらい忙しいときってありますよね。
スキンケアもただのルーティンになり、でもルーティンとして続けられているならましなほうで、クレンジングもせずに寝てしまったり、
大好きな本もただ文字を追うだけで内容が素通りしていって、いっこうに読み進められない本がたまるばかりだったり、
やりたいことリストとやるべきことリストはたくさんあるのに、どれも実行に移せなくて自分をだめな人間だと感じてしまったり。
世界との接点が曖昧でふわふわした不安定な心地になるよことがあります。
そんなときに、一文字一文字咀嚼するように丁寧に読むことで、またほんのりと世界の一員に加われたような気持ちになれる本があります。
石牟礼道子『春の海の記』です。
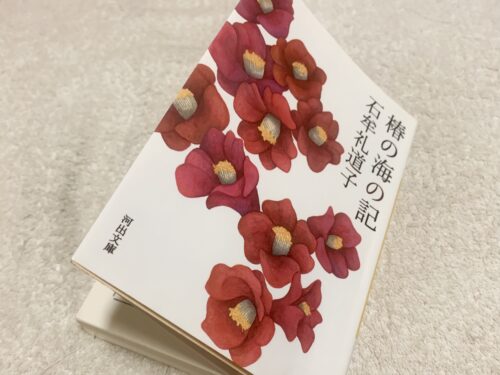
石牟礼道子さんといえば、水俣病患者を描いた『苦海浄土』がよく知られていますが、この本の舞台は水銀に侵される前の、豊かな自然があった頃の水俣です。
「言葉でこの世をあらわすことは、千年たっても万年たっても出来そうになかった」と書いていながら、まだ根源の深い世界からはなれ落ちきっていない4歳のみっちゃんの感じる世界が、作家石牟礼道子の手によって美しく表現されています。
好きな箇所を挙げれば本当にきりないのですが、例えば、
「溶け出してしまいそうな柔らかい空の下を、哀泣するかのようなその音色が、晩春の光に絡もうとしてはすべり落ち、すべり落ちして家並のあいだを抜け、青麦のあいだを越え、菜の花畠の上を越えて『美しき天然』のふしで、ぷうわ、ぷうわ、ぷうわっわ、ぷうわっわ、と波のようにゆっくりやってくる。芹の光る畦の上にやってくる。心の琴線に降りて来て、その音色がふいに絡みつく」 石牟礼道子『春の海の記』河出書房新社
どこから来た人たちなのかわからないサーカスの団員たちの奏でる音楽について表現する場面があります。音が光に絡もうとしてすべり落ち、最後に心の琴線に絡みつく。音色が内包するかなしみを、音と光と心のつながりでこんなふうに表現することができるのだと、はっとさせれるのです。
次の文も、こんな視点があるんだと、新しい世界の見方を教えてもらったような気持ちになりました。
「海に面したちいさなこの町の、晴天の日の暮らしの音というものは、かげろうといっしょにそのまんま、空へでもたちのぼっているのだろうけれども、厚い雨雲が、背面の竜山から中尾山をめぐりながら町をおおうようになると、音の抜ける上空がなくなってしまうのか、雨雲の下の中空のあたりに、暮らしの音が、地上のきずなをはなれた木霊となってひとりあそびをはじめるのだった」 石牟礼道子『春の海の記』河出書房新社
晴天の空に重たい雲が登場し、雨が降る前の様子が描かれているのですが、天にも抜けることができず地上にもとどまっていられない暮らしの音が、ひとりあそびをしているなんて、面白いですよね。
小説を読むのが好きという人でも、風景描写は苦手という声を聞くことがあります。でもこんなふうに人が混ざり込んだ描写なら読み飛ばすのはもったいないと思ってしまいます。
ただ自然を描写するだけではなく、自然と人の暮らしがひとつの風景として世界をつくっている様子が伝わってきます。
石牟礼道子さんは、夢とうつつ、目に見えるものと見えないものの間を自由に行き来し、理屈ではなく直接心に届くような言葉で伝えてくれます。
読み終わりたくない、と思ってしまう本に出合うことがたまにあります。この本もそのひとつで、時間をかけてゆっくり読みました。
こんなふうに世界を見ていたいと思うと同時に、こんなふうに世界を見る心の余裕を忘れずにいたいと思うのです。
たとえこんなに素敵な言葉で表現することができないにしても。
繰り返し読み続けたい本です。
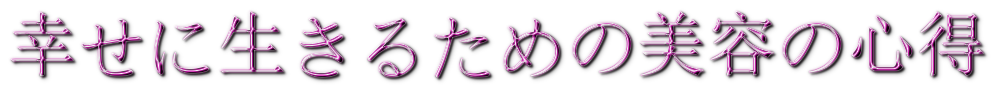



コメント